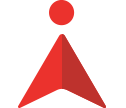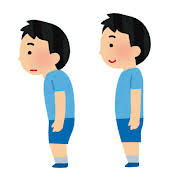はじめに
「花の女王」と言われるバラ。

その姿・香り等に魅了され、自宅に迎えて育ててみたい!という方、
読者の中にも居られるのではないでしょうか。
本記事は、バラを自宅に迎えて3年目のエンジニアによる、
バラを迎えるまでと迎えた後の苦労楽しみを通して、心が豊かになった話です。
迎える前の知識
正直言ってこれくらいでした。
- 棘がある
- 花束にすると特別感がすごい。色・本数で意味が様々。
- 結婚式でバラの装飾を使うと値段急上昇
ガーデニングも初心者で、枯らさずいけるんかな・・・と心配してました。
どの子にしよう?
どんな種類があるか、どんな選び方がいいか等々、とにかく調べまくっていました。
バラを多く扱う園芸店が車で30分程のところにあったので、五感で感じにいくことも数回・・・
検討の結果、次の観点を重視しました。
耐病性が高い
「栽培が比較的容易」につながると考えました。
始めてみたはいいものの病気に対して手を打てず枯らしてしまう・・・こんなことになると悲しいですよね。
調べていくと、近年のバラには耐病性が高いものも多いそうです。昔から親しまれた歴史のあるバラで風情を感じる・・・も良いですが、ガーデニング初心者としては、まず枯らさないことを目標にやってみることにしました。
自立する
これも「栽培が比較的容易」に加えて「切り花に向いてそう」な点が魅力に映りました。
バラには「つるバラ」という種類があります。
名前の通り「つる」を長く伸ばしていきますが、アサガオのように自らネットや柱につるを巻き付けて育つものではありません。フェンスやアーチに美しく仕立てられたバラは、人の手で導かれているのです(この作業を誘引と言います)。
ぜひやってみたかったのですが、筆者宅にそのような構造物が無かったため、自立するものに決めました。
また、切り花がくたっとなりにくく、花瓶に生けやすそうな点も良いと考えました。
落ち着いた色味
単に筆者の好みです。調べていると色々なものがあって面白かったです。
君に決めた!
検討の結果、次の2種を迎えることに決定しました。
筆者宅で撮影した写真で紹介します。
ビブラマリエ!

10cm程の大輪種で強香!病気に強い!花もち良し!これでもかと良い点を詰め込まれた品種です。
高さが2m近くまで伸びるので「バラって木なんだな」と感じさせられます。
ブルーグラビティ

7~8cm程で、枝先に2~4房付きます!香りはほんのり。
最大の魅力は色ですね。天然青バラも近いのでは?と感じさせられる。
バラを迎えてから
庭だけでなく家の中も華やかに
開花期は、庭はもちろんですが、切り花として家の中も華やかにしてくれます。
筆者はほぼ在宅勤務なので、このような花瓶をデスクに置き、バラの香りの中で仕事できます。最高!

冬以外は病気・虫と格闘
病気や虫の予防薬散布はしていますが、それでもゼロにはできず事後対処に追われてます。
本節でいくつか紹介します。
黒星病
病気に強い品種を選んで薬剤散布をしていても、これだけは防げませんでした。
黒星病にかかると、葉に黒っぽい斑点が多数現れ、放っておくと葉が黄色になり落ちてしまいます。元はカビが原因で、雨水の跳ね返りが原因とされます。落ちた葉からも伝染するので、早期対処が重要です。
対処はシンプルで、斑点の出た葉をすべて取り去り、落ちているものも掃除し、さらに周辺の葉も念のため取り去ること。もちろんその後の薬剤散布もです。
若くて柔らかい葉より、株元に近い硬い葉に症状が出やすいので、棘に要注意でなかなか手がかかります・・・梅雨時で庭仕事がおろそかになるときが一番発生しやすいのも厄介なところ。今後も戦いが続くこと間違いなしでしょう。
害虫
色々出ます。虫が苦手な人はここに一番覚悟が必要かもしれません。
ここでは筆者宅に現れた厄介者上位のみ紹介します(画像は苦手な方のために無しで)
スリップス:蕾や花に付いて汁を吸う1mm程度の虫。放っておくと花弁が茶褐色のシミや皺だらけになり、最悪開花しないまま枯れることもある。小さいため手で除去が難しく、切り花を家に持ち込むことも難しくなる。蕾が割れる前の薬剤散布等でかなり予防はできる。
チュウレンジハバチ:成虫は7~8mm程、幼虫は1cm程で芋虫のような見た目。成虫が茎に傷をつけて産卵し、茎を縦に割く孵化跡を残した幼虫の大群が、葉をスカスカになるまで食べる。筆者宅では薬剤散布していてもよく現れる。葉ごと幼虫をまとめて除去、成虫は箸や手で捕獲・捕殺
他も合わせれば7~8種は要注意な虫がいて、予防し、目を光らせ、退治する が止まりません。
生長を願って作業尽くし
病気・害虫対応の他、こんなことをやっています。
剪定
実は目的が様々で、ほぼ1年中やっています。
- 花がら摘み(病気・害虫の温床になりやすい)
- 摘蕾(蕾を摘む。花より生長を優先する場合に行う)
- 摘心(枝の先を摘む。枝分かれや脇芽の生長を促すために行う)
- 風通しを良くするための枝葉除去
- 冬(休眠期)越しのために、葉を全て取る+高さ半分以下までカット
追肥
植え付けた後、適宜肥料を与えること。冬の休眠期前の「寒肥」、春と秋の開花後の「お礼肥」が重要なタイミングだそうです。
成果にうっとり!
筆者宅のバラには、昨年度の冬に初めて「寒肥」をきちんと施したのですが、そのおかげか、これまでよりも圧倒的な生長・花付きを見せてくれました!頑張ってきてよかった・・・と感じます。

おわりに
花を楽しめるのはもちろんですが、
「ふとしたことに生命の神秘・逞しさを感じる」
これが、筆者にとってバラ栽培をはじめガーデニングを通しての「心の栄養」になっていると思います。
筆者は庭に植えていますが、鉢植えでもマンションでも栽培可能なはずです。
興味を持てた方、一緒に楽しみませんか?