人件費の会社負担とは?内訳・計算方法・節約のポイントを解説

人件費には給与のほか、会社が負担する社会保険料や福利厚生費なども含まれます。特に社会保険料は企業にとって大きな負担となり、人件費全体のコスト構造に直結します。会社負担の内訳を正しく理解することで、経営の効率化や将来の資金計画に役立ちます。
本記事では、人件費の会社負担について解説します。本記事をお読みいただくことで、自社の人件費管理の効率化に繋がりますので、是非とも最後までお読みください。
人件費の会社負担とは
人件費とは、企業が従業員に対して支払う全ての費用を指しますが、その中でも特に「会社負担分」と「従業員負担分」の違いを理解することが重要です。
「会社負担分」と「従業員負担分」の違い
人件費を理解する上で重要なのが、「会社負担分」と「従業員負担分」の違いです。これらは、企業が従業員に対して支払うコストの内訳を示しており、それぞれの役割を理解することで、経営戦略や人件費管理に役立ちます。
まず、「会社負担分」とは、企業が従業員に対して直接支払う給与や賞与に加え、社会保険料や福利厚生費など、企業が負担するコストを指します。これには、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険などの法定福利費が含まれ、企業の財務状況に大きな影響を与えます。
一方で、「従業員負担分」は、従業員が自らの給与から控除される部分を指します。具体的には、健康保険料や厚生年金保険料の一部が従業員の給与から引かれ、実際に手元に残る金額が減少します。このため、従業員にとっては、実質的な手取り額が重要なポイントとなります。
会社が負担する人件費の内訳
会社が負担する人件費は、主に給与や賞与、法定福利費、福利厚生費などから構成されています。これらの内訳を理解することは、企業の経営戦略やコスト管理において非常に重要です。
給与・賞与
人件費の中でも特に大きな割合を占めるのが、従業員に支払われる給与と賞与です。
給与は、従業員が労働の対価として受け取る基本的な報酬であり、月々の生活を支える重要な要素です。一方、賞与は年に数回支給される特別な報酬で、業績に応じて変動することが一般的です。これらの支出は、企業の人件費全体に大きな影響を与えるため、正確な管理が求められます。
給与は基本給に加え、残業手当や各種手当(通勤手当、家族手当など)を含むことが多く、これらの合計が従業員の総支給額となります。企業はこの総支給額に基づいて、社会保険料や税金を計算し、最終的に従業員に支払う金額を決定します。
法定福利費
法定福利費とは、法律に基づいて企業が従業員に対して負担しなければならない社会保険料のことを指します。具体的には、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などが含まれます。これらの費用は、企業の人件費において重要な位置を占めており、経営者にとっては避けて通れないコストとなります。
まず、健康保険は、従業員が病気や怪我をした際に医療費の一部を負担する制度です。企業は、従業員の給与に応じた保険料を支払う必要があります。さらに、厚生年金は、老後の生活を支えるための年金制度で、こちらも企業と従業員がそれぞれ半分ずつ負担します。
福利厚生費
福利厚生費は、企業が従業員に提供するさまざまなサービスや制度にかかる費用を指します。これには、健康診断や社員旅行、食事補助、育児休暇制度、教育研修費用などが含まれます。
福利厚生は、従業員のモチベーションや満足度を向上させるために重要な要素であり、企業の魅力を高める役割も果たします。
福利厚生費は、単に従業員の生活を支えるだけでなく、企業の競争力を維持するためにも欠かせません。特に優秀な人材を確保するためには、充実した福利厚生が求められることが多く、企業のブランドイメージにも影響を与えます。
したがって、福利厚生費は経営戦略の一環として位置づけられるべきです。
会社負担分の社会保険料の割合
社会保険料は、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の4つの主要な保険に分かれ、それぞれに異なる負担割合があります。これらの保険料は、企業の人件費を構成する重要な要素であり、経営戦略を考える上でも無視できません。
健康保険料 | 労使折半:会社と従業員がそれぞれ半分負担
健康保険料は、従業員が病気や怪我をした際に医療サービスを受けるための保険制度であり、企業にとって重要な人件費の一部を占めています。この保険料は、会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みになっています。
具体的には、健康保険料の総額を従業員と会社が等しく分担することで、双方の負担を軽減することが目的です。例えば、従業員の給与に基づいて算出された健康保険料が月額20,000円であった場合、会社と従業員はそれぞれ10,000円を負担します。
このように、健康保険料は企業の人件費において大きな割合を占めるため、経営者はその負担を正確に把握し、適切な資金計画を立てることが求められます。
厚生年金保険料 | 労使折半
厚生年金保険料は、企業が従業員の将来の年金受給を支えるために必要な保険料です。
この保険料は、企業と従業員がそれぞれ半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みになっています。具体的には、従業員の給与に基づいて計算され、企業がその半分を負担することで、従業員の老後の生活を支える重要な役割を果たしています。
厚生年金保険料の負担は、企業にとって大きなコストとなりますが、同時に従業員にとっても重要な保障となります。企業がこの保険料を適切に管理することは、従業員の福利厚生を充実させるだけでなく、企業の信頼性を高める要因にもなります。
雇用保険料 | 会社が多めに負担
雇用保険は、失業した際の生活を支えるための制度であり、企業が従業員を雇用する際には必ず加入が求められます。この保険料は、基本的に会社と従業員が負担する形となりますが、実際には会社が多めに負担することになります。
具体的には、雇用保険料の総額のうち、会社が負担する割合は従業員の負担分よりも高く設定されています。
例えば、雇用保険料の率は、従業員の給与に対して一定の割合で計算されますが、会社が負担する部分はその約1.5倍に相当します。このため、企業にとっては、雇用保険料が人件費の中で重要な位置を占めることになります。
労災保険料 | 全額会社負担
労災保険は、労働者が業務上の事故や病気により、療養や休業を余儀なくされた場合に、医療費や休業補償を提供するための保険制度です。この保険料は全額を会社が負担するため、企業にとっては重要なコストの一部となります。
労災保険料は、従業員の給与や業種によって異なるため、企業は自社の状況に応じた適切な保険料を把握する必要があります。具体的には、労働者の人数や業種に基づいて算出されるため、業種ごとのリスクに応じた保険料が設定されています。
人件費の会社負担を計算する方法
人件費の会社負担を正確に計算することは、企業の財務管理において非常に重要です。ここでは、各方法について解説します。
総支給額+会社負担分の社会保険料+福利厚生費
人件費の会社負担を正確に把握するためには、まずその計算方法を理解することが重要です。
基本的な計算式は「総支給額+会社負担分の社会保険料+福利厚生費」となります。この式を用いることで、企業が実際に従業員に対して支出している人件費の全体像を把握することができます。
まず、総支給額とは、従業員に支払われる基本給や手当、賞与などの合計を指します。これに加えて、会社が負担する社会保険料が含まれます。
社会保険料は、健康保険や厚生年金、雇用保険など、法律で定められた保険料であり、企業が従業員のために支払う必要があります。これらの保険料は、従業員の給与から控除される分と、会社が負担する分があり、労使折半の形をとるものも多いです。
一人あたりの会社負担額を求める手順
一人あたりの会社負担額を求めることは、企業の人件費管理において非常に重要です。正確な計算を行うことで、経営資源の最適化やコスト削減に繋がります。ここでは、その具体的な手順を解説します。
まず、基本となるのは「総支給額」です。これは、従業員に支払う給与や賞与の合計額を指します。次に、会社が負担する社会保険料を加算します。社会保険料には、健康保険や厚生年金、雇用保険などが含まれ、これらは企業が負担する割合が異なりますので、正確に把握しておく必要があります。
さらに、福利厚生費も考慮に入れます。福利厚生費は、従業員の生活の質を向上させるための費用であり、企業が提供する各種サービスや制度に関連しています。これらの費用を総支給額に加えることで、一人あたりの会社負担額を算出することができます。
具体的な計算式は以下の通りです:
一人あたりの会社負担額 = 総支給額 + 会社負担分の社会保険料 + 福利厚生費
この計算を行うことで、企業は各従業員に対する実際の人件費を把握し、経営戦略の立案や予算編成に役立てることができます。正確なデータを基にした判断は、企業の成長にとって欠かせない要素です。
会社負担人件費を効率的に管理する方法
企業が人件費を効率的に管理するためには、いくつかの具体的な方法があります。ここでは、各方法について解説します。
勤怠管理・給与計算ソフトの活用
人件費の管理において、勤怠管理や給与計算ソフトの活用は非常に重要です。
これらのツールを導入することで、手作業によるミスを減らし、効率的なデータ管理が可能になります。特に、勤怠管理ソフトは従業員の出勤状況や労働時間を正確に把握するための基盤となり、給与計算の正確性を高める役割を果たします。
また、給与計算ソフトは、法定福利費や社会保険料の計算を自動化することで、経理部門の負担を軽減します。これにより、従業員の給与明細を迅速に作成できるだけでなく、税務申告や社会保険の手続きもスムーズに行えるようになります。
導入にあたっては、企業の規模や業種に応じた適切なソフトを選ぶことが重要です。多機能なものからシンプルなものまで様々な選択肢があるため、自社のニーズに合ったものを見極めることが求められます。
社会保険料の見直し
社会保険料は、企業にとって大きな負担となる費用の一つです。
特に、健康保険や厚生年金保険などの法定福利費は、従業員の給与に対して一定の割合で計算されるため、従業員数が増えるほどその負担も増加します。したがって、社会保険料の見直しは、企業の人件費を効率的に管理するための重要なステップとなります。
まず、社会保険料の見直しを行う際には、現在の保険料率や適用範囲を正確に把握することが必要です。これにより、無駄な支出を削減するための具体的な対策を講じることができます。
また、社会保険料の見直しには、従業員とのコミュニケーションも欠かせません。保険の内容や変更点についてしっかりと説明し、理解を得ることで、従業員のモチベーションを維持しつつ、企業の負担を軽減することができます。
福利厚生の適正化
福利厚生は、従業員のモチベーションや満足度を向上させるために重要な要素ですが、企業にとってはコストがかかる部分でもあります。
まず、福利厚生の内容を見直すことが必要です。従業員が実際に利用している福利厚生と、あまり利用されていないものを把握し、必要なサービスに絞ることで、コストを削減できます。
また、従業員の意見を取り入れ、どのような福利厚生が求められているのかを調査することも重要です。これにより、従業員の満足度を維持しながら、無駄な支出を減らすことが可能になります。
さらに、福利厚生の提供方法を工夫することも一つの手段です。例えば、従業員が自分のニーズに合わせて選べる「選択制福利厚生」を導入することで、個々のライフスタイルに合ったサービスを提供しつつ、企業側の負担を軽減することができます。
業務効率化・外注化による人件費削減
企業が人件費を削減するための有効な手段の一つが、業務効率化と外注化です。
まず、業務効率化について考えてみましょう。業務プロセスの見直しや改善を行うことで、従業員の生産性を向上させることができます。例えば、業務フローを整理し、重複作業を排除することで、時間を短縮し、結果として人件費を削減することができます。また、ITツールやソフトウェアを導入することで、業務の自動化を進めることも一つの手段です。
次に、外注化のメリットについてです。特定の業務を外部の専門業者に委託することで、内部リソースを効率的に活用することができます。例えば、経理やITサポート、マーケティングなどの業務を外注することで、専門的な知識を持つプロフェッショナルに任せることができ、結果としてコスト削減につながります。外注化は、固定費を変動費に変えることができるため、経営の柔軟性を高める効果もあります。
まとめ
人件費の会社負担について理解することは、企業経営において非常に重要です。人件費は単に従業員の給与だけでなく、社会保険料や福利厚生費など多岐にわたる要素から成り立っています。これらの内訳を正確に把握することで、企業はコスト管理を効率化し、将来的な資金計画を立てやすくなります。
特に社会保険料は、企業にとって大きな負担となるため、その割合や負担の仕組みを理解することが不可欠です。また、会社負担分の人件費を計算する方法や、効率的な管理手法を取り入れることで、無駄なコストを削減し、経営の健全化を図ることが可能です。
本記事で紹介した内容を参考に、自社の人件費管理を見直し、より効率的な運営を目指していただければ幸いです。人件費の適正化は、企業の競争力を高めるための重要なステップですので、ぜひ実践してみてください。

Fairgrit®メディア編集部です。
SES業界にまつわる内容をはじめ、ITに関するお役立ち情報を不定期にお届けいたします!
私どもの情報が皆さまのなにがしかのお役に立てれば嬉しいです!
当編集部が企画・執筆・公開する記事は情報の公平性・有用性・再利用性に配慮した上で、十分な注意と調査のもと可能な限り客観的 かつ 一般的な情報・状況となるよう制作いたしております。
そのため、弊社としての見解やスタンス/ポリシーとは異なる内容や記載が含まれる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
また、さまざまな要因により事実と異なる内容や古い情報が含まれてしまう可能性もございます。恐れ入りますが、記事中の情報につきましてはご自身の判断と責任の元でご利用ください。
(弊社 ならびに 当編集部は、当アカウントがご提供しているコラム記事に関して、明示的か暗黙的かを問わず一切保証をいたしておりません。記事中の情報をご利用頂いたことにより生じたいかなる損害も負いかねます)


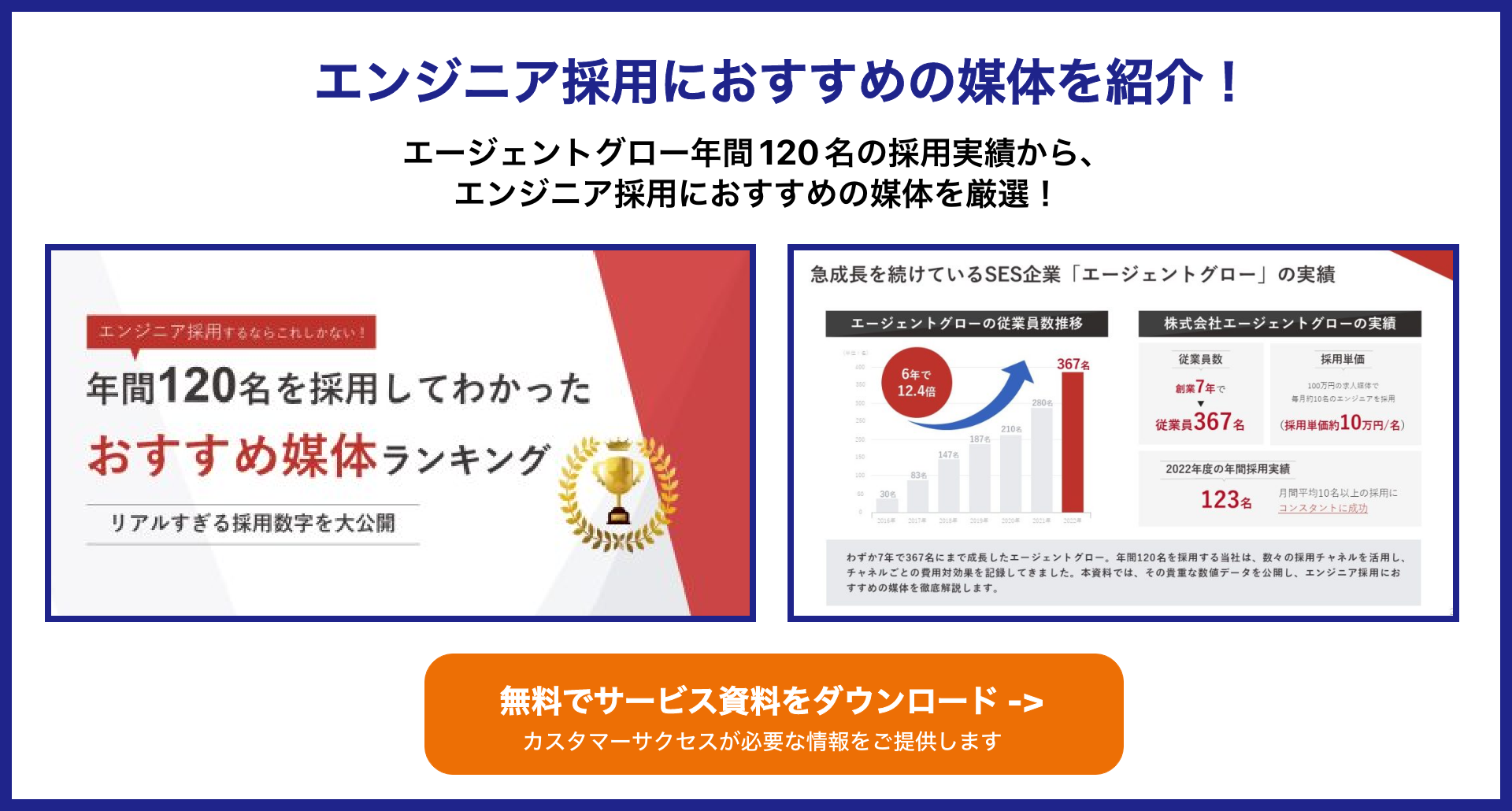




-237x133.png)

-237x133.png)





-473x266.jpg)
-473x266.jpg)

