裁量労働制の勤務時間の仕組みとは?種類別の導入の流れを解説

裁量労働制の勤務時間は、実際に働いた時間ではなく「みなし労働時間」として扱われる点が特徴です。一定の時間を働いたとみなされるため、出退勤に縛られず自分のペースで業務を進められます。
本記事では、裁量労働制の勤務時間の扱いについて詳しく解説します。本記事をお読みいただくことで、自社の労務規定を策定する上で参考になるはずですので、是非とも最後までお読みください。
裁量労働制の勤務時間の仕組みとは
裁量労働制は、労働者が自らの裁量で業務を進めることができる制度であり、その勤務時間の扱いには特有の仕組みがあります。
一般的な労働時間制度では、実際に働いた時間に基づいて給与が支払われますが、裁量労働制では「みなし労働時間」が適用されます。これは、労働者が一定の時間を働いたとみなされるため、出退勤の時間に縛られず、自分のペースで業務を進めることができるという特徴があります。
具体的には、裁量労働制では、業務の内容や性質に応じて、あらかじめ定められた時間が「みなし労働時間」として設定されます。この時間は、実際の労働時間とは異なる場合がありますが、労働者はその時間内で業務を遂行することが求められます。
裁量労働制の種類とは
裁量労働制には主に二つの種類が存在します。これらは「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」と呼ばれ、それぞれ異なる業務内容や対象者に応じて適用されます。
専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、特定の専門的な業務に従事する労働者に対して適用される制度です。この制度の特徴は、労働者が自らの専門知識や技能を活かし、業務を遂行する際に、勤務時間を柔軟に設定できる点にあります。
具体的には、労働者は一定の「みなし労働時間」が定められ、その時間内であれば自由に業務を進めることが可能です。この制度は、主に研究開発やIT関連、法律、会計などの専門職に適用されることが多く、労働者は自分のペースで業務を進めることができるため、創造性や生産性の向上が期待されます。
企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、主に企画や調査、分析などの業務に従事する労働者を対象とした制度です。この制度の特徴は、労働者が自らの裁量で業務を進めることができる点にあります。
具体的には、労働者は一定の「みなし労働時間」が設定され、その時間内であれば出退勤の時間に縛られることなく、自分のペースで仕事を進めることが可能です。
この制度は、特に創造的な業務やプロジェクトベースの仕事において、柔軟な働き方を実現するために導入されることが多いです。労働者は、自分の業務の進捗に応じて時間を調整できるため、効率的に業務を遂行することが期待されます。
専門業務型裁量労働制を導入する流れ
専門業務型裁量労働制を導入する際には、いくつかのステップを踏む必要があります。この制度は、特定の専門的な業務に従事する労働者に対して適用されるため、導入プロセスは慎重に進めることが求められます。以下にその流れを詳しく解説します。
対象であることを確認する
専門業務型裁量労働制を導入する際の最初のステップは、対象となる業務や職種がこの制度に適しているかを確認することです。
裁量労働制は、特定の職務に従事する労働者に対して適用されるため、すべての業務が対象になるわけではありません。具体的には、専門的な知識や技術を必要とする業務や、企画や開発などの創造的な業務が該当します。
まずは、自社の業務内容を見直し、裁量労働制の適用が可能な職種を特定します。これには、業務の性質や従業員の役割を詳細に分析することが求められます。また、労働者が自らの裁量で業務を進めることができる環境が整っているかどうかも重要なポイントです。
さらに、裁量労働制を導入することで、業務の効率化や従業員のモチベーション向上が期待できるため、導入のメリットをしっかりと把握しておくことも大切です。対象業務が明確になったら、次のステップとして労使協定の締結に進むことができます。
労使協定を結ぶ
専門業務型裁量労働制を導入する際には、労使協定を結ぶことが不可欠です。この協定は、労働者と使用者の間で裁量労働制の適用に関する合意を形成するものであり、労働条件や勤務時間の取り決めを明確にする役割を果たします。
労使協定を結ぶためには、まず労働者側の代表者と使用者側の代表者が集まり、協議を行う必要があります。この際、裁量労働制の導入目的やそのメリット、デメリットについて十分に話し合い、労働者が納得できる内容にすることが重要です。協定の内容には、みなし労働時間や業務の範囲、労働者の権利保護に関する事項などが含まれます。
個別の労働契約や就業規則などの整備をする
専門業務型裁量労働制を導入する際には、個別の労働契約や就業規則の整備が不可欠です。このプロセスは、労働者と雇用者の権利と義務を明確にし、裁量労働制の特性を反映させるために重要です。
まず、個別の労働契約においては、労働時間や業務内容、給与体系などを具体的に記載する必要があります。これにより、労働者は自分の業務に対する期待や責任を理解しやすくなります。また、裁量労働制の特性上、労働時間の管理が従来の方法とは異なるため、労働契約にはその旨を明記し、誤解を避けることが求められます。
さらに、就業規則の整備も重要です。就業規則には、裁量労働制の適用範囲や労働時間の考え方、休暇制度などを詳細に記載することで、全従業員が同じルールのもとで働くことができるようになります。
労働基準監督署に労使協定の届出を行う
専門業務型裁量労働制を導入する際には、労使協定を結んだ後、必ず労働基準監督署にその協定を届け出る必要があります。この手続きは、労働基準法に基づくものであり、適切な手続きを踏むことで、法的なトラブルを避けることができます。
届出を行う際には、労使協定の内容が正確であることを確認し、必要な書類を整えることが重要です。具体的には、労使協定の写しや、協定に基づく労働条件の詳細を記載した書類を提出します。これにより、労働基準監督署は協定の内容を確認し、適法性を判断します。
労働者の同意を得る
専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制を導入する際には、労働者の同意を得ることが不可欠です。
この同意は、労働者が新しい勤務形態に対して理解し、納得した上で働くことを保証するための重要なステップです。労働者が裁量労働制の内容やその影響を十分に理解していない場合、後々のトラブルや不満の原因となることがあります。
同意を得るためには、まず裁量労働制の仕組みや特徴、労働条件の変更点について、労働者に対して丁寧に説明することが求められます。具体的には、みなし労働時間の設定や、実際の業務内容、期待される成果などを明確に伝えることが重要です。
また、労働者が疑問や不安を持っている場合には、それに対する回答をしっかりと行い、信頼関係を築くことが必要です。
企画業務型裁量労働制を導入する流れ
企画業務型裁量労働制を導入する際には、いくつかのステップを踏む必要があります。この制度は、特定の業務に従事する労働者に対して、労働時間を柔軟に設定できる仕組みです。以下に、導入の流れを詳しく解説します。
対象業務があることを確認する
企画業務型裁量労働制を導入する際には、まず対象業務が存在することを確認することが重要です。この制度は、特定の業務に従事する労働者に対して適用されるため、どの業務が対象となるのかを明確にする必要があります。
具体的には、企画や調査、分析、開発などの業務が該当しますが、これらの業務が実際に行われているかどうかを確認することが第一歩です。
対象業務の確認は、労働者が裁量労働制のもとで自律的に業務を進めるための基盤となります。業務内容が明確であれば、労働者は自分の裁量で時間を管理し、効率的に業務を遂行することが可能になります。また、対象業務の確認は、労使協定を結ぶ際にも必要なステップであり、後の手続きにおいても重要な役割を果たします。
労使委員会の設置・決議を行う
企画業務型裁量労働制を導入する際には、労使委員会の設置とその決議が重要なステップとなります。
労使委員会は、労働者と使用者の代表が集まり、労働条件や労働環境について話し合う場です。この委員会を設置することで、労働者の意見を反映させることができ、より良い労働環境を築くための基盤を作ることができます。
労使委員会の設置にあたっては、まず委員の選出を行います。労働者側からは代表者を選び、使用者側からも適切なメンバーを選定します。
委員会が設置された後は、裁量労働制の導入に関する具体的な内容や条件について議論を行い、合意形成を図ります。この過程で、労働者の権利や福利厚生についても十分に考慮されるべきです。
個別の労働契約や就業規則等の整備する
専門業務型裁量労働制を導入する際には、個別の労働契約や就業規則の整備が不可欠です。まず、労働契約には裁量労働制の適用に関する具体的な内容を明記する必要があります。
これには、みなし労働時間や業務内容、給与の取り決めなどが含まれます。労働者が自分の業務をどのように進めるかを理解しやすくするために、具体的な業務範囲や期待される成果についても記載することが重要です。
さらに、就業規則についても見直しが求められます。裁量労働制を導入することで、従来の出退勤管理が緩和されるため、労働時間の管理方法や評価基準を明確にする必要があります。これにより、従業員が自分の裁量で業務を進める際の指針となり、トラブルを未然に防ぐことができます。
所轄労働基準監督署に決議届を届け出る
企画業務型裁量労働制を導入する際には、労使委員会での決議が必要です。この決議が完了した後、次のステップとして所轄の労働基準監督署に決議届を届け出ることが求められます。この手続きは、裁量労働制の適用を正式に認めてもらうために不可欠です。
決議届には、労使委員会での決議内容や、裁量労働制を導入する業務の具体的な内容、適用される労働者の範囲などが記載されます。届け出を行うことで、労働基準監督署はその内容を確認し、適法性を審査します。このプロセスを経ることで、企業は法的に認められた裁量労働制を運用することが可能となります。
労働者の同意を得る
専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制を導入する際には、労働者の同意を得ることが不可欠です。この同意は、労働者が新しい勤務形態に対して理解し、納得した上で働くことを保証するための重要なステップです。労働者が裁量労働制の内容やその影響を十分に理解していない場合、後々のトラブルや不満の原因となる可能性があります。
同意を得るためには、まず裁量労働制の仕組みや特徴、そしてそのメリット・デメリットについて労働者にしっかりと説明することが重要です。
具体的には、みなし労働時間の設定や、実際の業務内容、期待される成果などを明確に伝え、労働者が自分の働き方にどのように影響するかを理解できるようにします。
裁量労働制を導入する時の注意点
裁量労働制を導入する際には、いくつかの重要な注意点があります。ここでは、各注意点について解説します。
実働時間とみなし労働時間の差を確認する
裁量労働制を導入する際には、実働時間とみなし労働時間の差をしっかりと確認することが重要です。
裁量労働制では、労働者が実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定められた「みなし労働時間」に基づいて給与が支払われます。
このため、実働時間がみなし労働時間を下回る場合、労働者は自分のペースで業務を進めることができる一方で、逆に実働時間がみなし労働時間を超える場合には、過重労働のリスクが生じることになります。
企業は、みなし労働時間が適切に設定されているかを確認し、実働時間とのバランスを取る必要があります。特に、業務の内容や労働者の職務に応じて、みなし労働時間を見直すことが求められる場合もあります。
従業員の健康管理を怠らない
裁量労働制を導入する際には、従業員の健康管理が非常に重要です。裁量労働制では、労働時間が「みなし労働時間」として扱われるため、実際の労働時間が把握しづらくなります。
企業側は、従業員の健康を守るために、定期的な健康診断やメンタルヘルス対策を実施することが重要です。
また、労働時間の管理を徹底し、必要に応じて労働時間の見直しや業務の調整を行うことも求められます。従業員が健康であることは、企業の生産性にも直結するため、健康管理は単なる義務ではなく、企業の成長戦略の一環として捉えるべきです。
労働時間の把握が必須である
裁量労働制を導入する際には、労働時間の把握が非常に重要です。裁量労働制では、実際に働いた時間ではなく「みなし労働時間」が適用されるため、従業員がどれだけの時間を業務に費やしているかを正確に把握することが求められます。
これは、労働者の権利を守るためだけでなく、企業側が適切な労務管理を行うためにも欠かせません。具体的には、労働時間の把握を怠ると、従業員の過重労働や健康問題を引き起こす可能性があります。また、労働基準法に基づく適切な労働時間の管理ができていない場合、企業は法的なリスクを抱えることにもなりかねません。
そのため、裁量労働制を導入する際には、労働時間の記録や管理方法を明確にし、従業員に対してもその重要性を周知することが必要です。
適用職種が限定されている
裁量労働制は、すべての職種に適用されるわけではなく、特定の職種に限定されています。
具体的には、専門的な知識や技術を要する業務や、創造的な業務が対象となります。これにより、裁量労働制を導入する企業は、どの職種がこの制度に適しているかを慎重に見極める必要があります。
例えば、専門業務型裁量労働制は、弁護士や医師、研究者など、専門的なスキルを持つ職種に適用されることが多いです。一方、企画業務型裁量労働制は、マーケティングや商品企画、プロジェクトマネジメントなど、創造的な業務に従事する職種が対象となります。
このように、裁量労働制はその性質上、業務内容や職種によって適用が異なるため、企業は自社の業務に合った制度を選択することが重要です。
まとめ
裁量労働制は、従来の労働時間の概念を大きく変える制度であり、特に専門的な業務や企画業務に従事する労働者にとっては、自分のペースで働くことができる大きなメリットがあります。みなし労働時間として扱われるため、出退勤の時間に縛られず、柔軟な働き方が可能となります。しかし、その導入にはいくつかの注意点が存在します。
本記事を通じて、裁量労働制の勤務時間の仕組みや導入の流れについて理解を深めていただけたことと思います。自社の労務規定を策定する際には、これらのポイントを参考にし、適切な運用を心がけてください。柔軟な働き方を実現するために、裁量労働制を上手に活用していきましょう。
参考:時間コストを意識して人生を変える | 日本一店長のアイシープ

Fairgrit®メディア編集部です。
SES業界にまつわる内容をはじめ、ITに関するお役立ち情報を不定期にお届けいたします!
私どもの情報が皆さまのなにがしかのお役に立てれば嬉しいです!
当編集部が企画・執筆・公開する記事は情報の公平性・有用性・再利用性に配慮した上で、十分な注意と調査のもと可能な限り客観的 かつ 一般的な情報・状況となるよう制作いたしております。
そのため、弊社としての見解やスタンス/ポリシーとは異なる内容や記載が含まれる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
また、さまざまな要因により事実と異なる内容や古い情報が含まれてしまう可能性もございます。恐れ入りますが、記事中の情報につきましてはご自身の判断と責任の元でご利用ください。
(弊社 ならびに 当編集部は、当アカウントがご提供しているコラム記事に関して、明示的か暗黙的かを問わず一切保証をいたしておりません。記事中の情報をご利用頂いたことにより生じたいかなる損害も負いかねます)


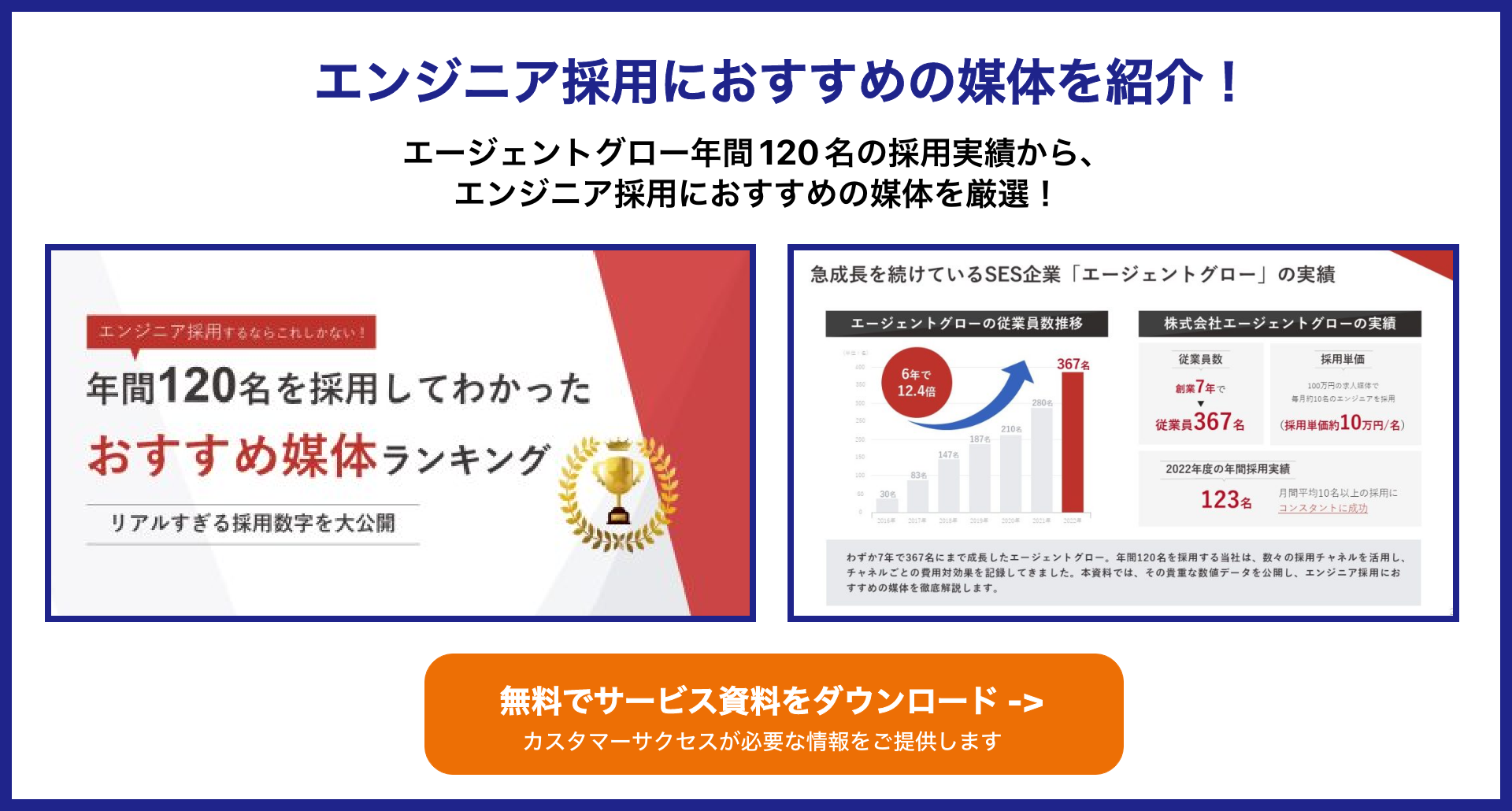




-237x133.png)

-237x133.png)





-473x266.jpg)
-473x266.jpg)

