裁量労働制のメリット・デメリットとは?企業側と従業員別で解説!

裁量労働制は、働く時間ではなく成果に基づいて評価される働き方として注目されています。特に専門職や企画業務に多く導入されており、自分の裁量でスケジュールを組める点が大きな魅力です。
本記事では、裁量労働制のメリットについて詳しく解説します。本記事をお読みいただくことで、自社の労務規定を策定する上で参考になるはずですので、是非とも最後までお読みください。
INDEX
企業側の裁量労働制のメリット
裁量労働制は、企業にとっても多くのメリットをもたらします。ここでは、各メリットについて解説します。
人件費を管理しやすい
裁量労働制の導入により、企業側は人件費の管理が容易になるという大きなメリットがあります。従来の労働時間に基づく賃金体系では、残業や休日出勤などの変動が人件費に直接影響を与えるため、予算管理が難しくなることがしばしばあります。
しかし、裁量労働制では、成果に基づいて評価されるため、労働時間に依存しない固定的なコスト管理が可能になります。
この制度を採用することで、企業は従業員の働き方を柔軟に調整できるため、必要に応じて人員配置を見直すことができます。
特に、プロジェクトの進行状況や業務の繁忙期に応じて、リソースを最適化することができるため、無駄な人件費を削減することが期待できます。
優秀な人材を集めやすい
裁量労働制は、企業が優秀な人材を集める上で非常に効果的な制度です。
特に専門職やクリエイティブな職種においては、従業員が自分の裁量で働くことができる環境が求められています。この制度を導入することで、企業は柔軟な働き方を提供し、他社との差別化を図ることができます。
また、裁量労働制は、成果に基づく評価が行われるため、能力の高い人材にとって魅力的な選択肢となります。自分のペースで仕事を進められることで、モチベーションが向上し、結果として企業の成長にも寄与することが期待されます。
生産性が向上する可能性が高い
裁量労働制の導入により、企業側は生産性の向上を期待することができます。
従来の労働時間に基づく評価から、成果に基づく評価へとシフトすることで、従業員は自らのペースで業務を進めることが可能になります。
また、裁量労働制では、従業員が自分の裁量で仕事を進めるため、業務の優先順位を柔軟に変更することができます。これにより、急なプロジェクトやクライアントからの要望にも迅速に対応できるため、企業全体の機動力が向上します。
従業員側の裁量労働制のメリット
裁量労働制は、従業員にとって多くのメリットを提供します。ここでは、各メリットについて解説します。
働き方の自由度が高くなる
裁量労働制の最大の魅力の一つは、従業員が自分の働き方を自由に選択できる点です。
従来の労働時間に縛られることなく、自分のライフスタイルや業務の特性に応じて、最適なスケジュールを組むことが可能になります。
また、裁量労働制は、特に専門職やクリエイティブな業務において、その効果を発揮します。例えば、アイデアを練るために静かな環境が必要な場合や、特定の時間帯に集中して作業を行いたい場合など、従業員は自分の裁量で最適な環境を整えることができます。
ライフワークバランスを取りやすくなる
裁量労働制の大きなメリットの一つは、従業員がライフワークバランスを取りやすくなる点です。従来の労働時間に縛られず、自分の裁量で働く時間を調整できるため、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。
例えば、子育て中の従業員は、子どもが学校に行っている間に集中して仕事を進め、放課後は家族と過ごす時間を確保することができます。
また、趣味や自己啓発のための時間を持つことで、仕事に対するモチベーションも高まります。このように、裁量労働制は従業員が自分の生活に合わせた働き方を実現する手助けをしてくれるのです。
企業側の裁量労働制のデメリット
裁量労働制は多くのメリットを企業にもたらしますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。ここでは、各デメリットについて解説します。
余計な工数がかかる
裁量労働制は、従業員に自由な働き方を提供する一方で、企業側にとっては余計な工数が発生する可能性があります。
特に、労働時間の管理が従来の固定時間制と異なるため、従業員の働き方を把握するための新たな仕組みやプロセスが必要になります。
また、裁量労働制を導入する際には、労使協定の締結や就業規則の整備が求められます。これらの手続きは、企業にとって時間とリソースを消費する要因となります。
特に、法令遵守を徹底するためには、専門的な知識を持つ人材が必要となる場合もあり、結果的にコストがかさむこともあります。
チームワークを高めることが難しい
裁量労働制の導入には多くのメリットがありますが、企業側にとってのデメリットの一つとして「チームワークを高めることが難しい」という点が挙げられます。
裁量労働制では、各従業員が自分の裁量で働く時間や方法を決定するため、個々の業務が独立して進行しがちです。このため、チーム全体の連携が取りづらくなることがあります。
特に、プロジェクトベースでの業務が多い企業では、メンバー間のコミュニケーションが重要です。しかし、裁量労働制では各自が異なる時間に働くことが多く、情報共有や意見交換がスムーズに行われない場合があります。
従業員側の裁量労働制のデメリット
裁量労働制は多くのメリットを提供する一方で、従業員にとっていくつかのデメリットも存在します。ここでは、各デメリットについて解説します。
労働時間が伸びやすい
裁量労働制の導入により、従業員は自分の裁量で働く時間を決めることができますが、その反面、労働時間が伸びやすいというデメリットも存在します。
特に、成果を重視する働き方であるため、目標達成のために必要以上に働いてしまうケースが多く見受けられます。自分のペースで仕事を進められる一方で、時間の管理が難しくなり、気づけば長時間労働に陥ってしまうことも少なくありません。
また、裁量労働制では、業務の進捗や成果に対するプレッシャーが強くなることがあります。このため、従業員は「もっと働かなければならない」という心理的な負担を感じやすく、結果として労働時間が延びる傾向があります。
残業代が出ない
裁量労働制の大きなデメリットの一つは、残業代が支払われない点です。通常の労働時間制では、労働者が一定の時間を超えて働いた場合、残業代が発生します。
しかし、裁量労働制では、労働時間ではなく成果に基づいて評価されるため、実際に働いた時間に関係なく、残業代が支給されないことが一般的です。
この制度の下では、従業員は自分の裁量で働く時間を決めることができるため、自己管理が求められます。しかし、成果を上げるために長時間働くことが常態化すると、労働者は過労やストレスを抱えるリスクが高まります。
他の労働時間制との違い
裁量労働制は、他の労働時間制と比較して独自の特徴を持っています。ここでは、各違いについて解説します。
固定時間制
固定時間制は、労働者があらかじめ定められた時間に出勤し、同じ時間に退勤する働き方を指します。この制度では、労働時間が明確に設定されており、通常は1日8時間、週40時間が一般的な基準となっています。
固定時間制の最大の特徴は、労働者が一定の時間内に業務を遂行することが求められるため、時間管理が容易である点です。
企業側にとっては、労働時間が明確であるため、労働コストの予測が立てやすく、計画的な人員配置が可能になります。また、従業員にとっても、勤務時間が決まっているため、プライベートの時間を確保しやすいというメリットがあります。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、従業員が始業・終業の時間を自分の裁量で決定できる制度です。この制度の特徴は、コアタイムと呼ばれる必ず出勤しなければならない時間帯を設け、その前後の時間を自由に選べる点にあります。
フレックスタイム制のメリットは、従業員が自分の生活リズムに合わせて働けるため、ストレスの軽減やモチベーションの向上につながることです。
また、通勤ラッシュを避けることができるため、時間の有効活用が図れます。企業側にとっても、従業員の生産性を高める効果が期待できるため、導入が進んでいます。
変形労働時間制
変形労働時間制は、労働時間を一定の期間内で柔軟に設定できる制度です。
この制度では、労働者が特定の期間において、労働時間を変動させることが可能であり、例えば、繁忙期には長時間働き、閑散期には短時間勤務をすることができます。
変形労働時間制は、特に季節や業務の変動が大きい業界において有効です。例えば、観光業や農業などでは、繁忙期と閑散期が明確に分かれているため、労働時間を柔軟に調整することで、無駄な人件費を抑えることができます。
高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度は、特定の専門的な職務に従事する従業員に対して、労働時間の規制を適用しない働き方を認める制度です。
この制度は、主に高度な専門知識や技術を持つ職業に適用され、例えば、弁護士や医師、研究者などが該当します。裁量労働制と同様に、成果に基づいて評価されるため、従業員は自らの裁量で働く時間や方法を選択することができます。
この制度の大きな特徴は、労働時間の上限が設けられていないため、従業員は自分のペースで仕事を進めることができる点です。これにより、専門職においては、プロジェクトの進行状況や成果に応じて柔軟に働くことが可能となります。
裁量労働制を導入する流れとは
裁量労働制を企業に導入する際には、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、各流れについて解説します。
労使協定を締結する
裁量労働制を導入するための第一歩は、労使協定の締結です。この協定は、企業と従業員の代表が合意するもので、裁量労働制の適用に関する具体的な条件やルールを定める重要な文書です。
労使協定を結ぶことで、双方の理解を深め、制度の運用におけるトラブルを未然に防ぐことができます。労使協定には、裁量労働制の対象となる業務や職種、労働時間の算定方法、評価基準などが明記されます。
また、従業員がどのように成果を上げるかについても具体的に示すことで、透明性を確保し、従業員のモチベーション向上にも寄与します。
労働契約・就業規則を整備する
裁量労働制を導入する際には、労働契約や就業規則の整備が不可欠です。
まず、労働契約には裁量労働制の適用範囲や労働時間の考え方、評価基準などを明確に記載する必要があります。これにより、従業員が自分の業務に対する理解を深め、安心して働ける環境を整えることができます。
さらに、就業規則についても同様に、裁量労働制に関する具体的なルールや手続き、労働条件を詳細に記載することが求められます。特に、成果の評価方法や業務の進捗管理の仕組みを明確にすることで、従業員が自分の業務に対する責任感を持ちやすくなります。
労働基準監督署長に届け出を出す
裁量労働制を導入する際には、労働基準監督署長に届け出を行うことが必要です。
この手続きは、労働基準法に基づくものであり、企業が裁量労働制を適用するためには、法的な要件を満たす必要があります。届出を行うことで、企業は労働基準監督署からの承認を得ることができ、適切な運用が行われていることを示すことができます。
届け出の内容には、裁量労働制を適用する業務の範囲や対象者、労働時間の算定方法などが含まれます。また、企業はこの届出を行う前に、労使協定を締結し、従業員との合意を得ることが求められます。
対象者に同意を得る
裁量労働制を導入する際には、対象となる従業員からの同意を得ることが不可欠です。
この同意は、労使間の信頼関係を築くためにも重要なステップとなります。従業員が裁量労働制の内容やその影響を理解し、自らの意思で同意することが求められます。
具体的には、裁量労働制の導入に関する説明会を開催し、制度の目的やメリット、デメリットについて詳しく説明することが効果的です。また、従業員が疑問や不安を持つ場合には、個別に相談できる機会を設けることも大切です。
健康・福祉確保措置などを講じる
裁量労働制を導入する際には、従業員の健康や福祉を確保するための措置を講じることが重要です。
裁量労働制は、従業員が自分の裁量で働く時間を決定できる一方で、労働時間が不規則になりがちであるため、過労やストレスのリスクが高まる可能性があります。
まず、定期的な健康診断の実施が求められます。これにより、従業員の健康状態を把握し、早期に問題を発見することができます。
また、メンタルヘルスに関するサポート体制を整えることも重要です。カウンセリングサービスやストレスチェックを導入することで、従業員が安心して働ける環境を提供することができます。
まとめ
裁量労働制は、企業と従業員の双方にとって多くのメリットを提供する働き方です。企業側にとっては、人件費の管理がしやすく、優秀な人材を集めやすい環境を整えることができるため、競争力を高める要素となります。また、従業員にとっては、働き方の自由度が高まり、ライフワークバランスを取りやすくなることが大きな魅力です。
しかし、裁量労働制にはデメリットも存在します。企業側は余計な工数がかかる場合や、チームワークを高めることが難しくなることがあります。一方、従業員側では労働時間が伸びやすく、残業代が出ないというリスクも考慮しなければなりません。
このように、裁量労働制はその特性から、導入に際しては慎重な検討が必要です。企業は自社の状況や従業員のニーズをしっかりと把握し、適切な運用を行うことで、より良い労働環境を実現することができるでしょう。

Fairgrit®メディア編集部です。
SES業界にまつわる内容をはじめ、ITに関するお役立ち情報を不定期にお届けいたします!
私どもの情報が皆さまのなにがしかのお役に立てれば嬉しいです!
当編集部が企画・執筆・公開する記事は情報の公平性・有用性・再利用性に配慮した上で、十分な注意と調査のもと可能な限り客観的 かつ 一般的な情報・状況となるよう制作いたしております。
そのため、弊社としての見解やスタンス/ポリシーとは異なる内容や記載が含まれる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
また、さまざまな要因により事実と異なる内容や古い情報が含まれてしまう可能性もございます。恐れ入りますが、記事中の情報につきましてはご自身の判断と責任の元でご利用ください。
(弊社 ならびに 当編集部は、当アカウントがご提供しているコラム記事に関して、明示的か暗黙的かを問わず一切保証をいたしておりません。記事中の情報をご利用頂いたことにより生じたいかなる損害も負いかねます)


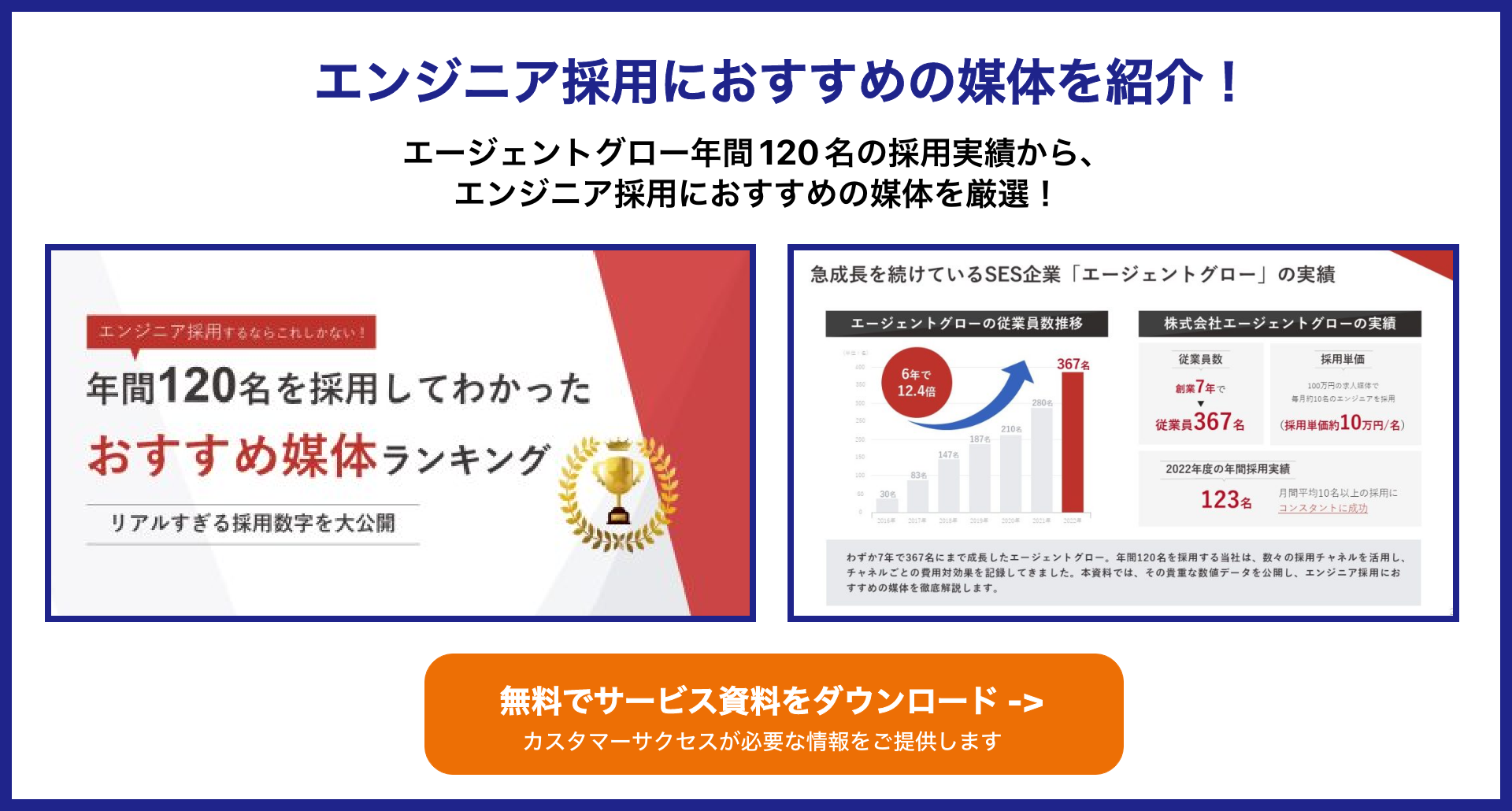




-237x133.png)

-237x133.png)





-473x266.jpg)
-473x266.jpg)

